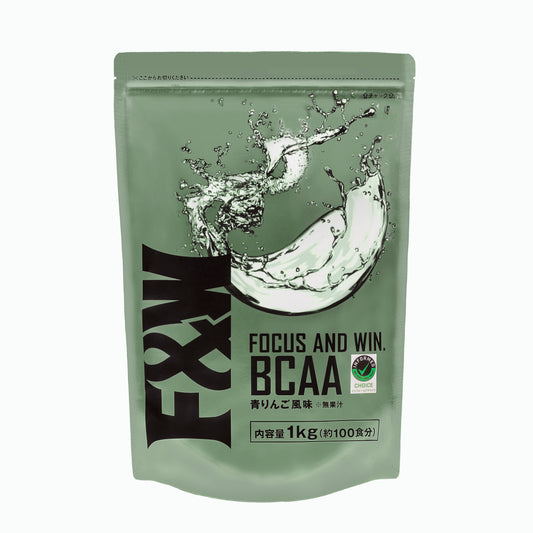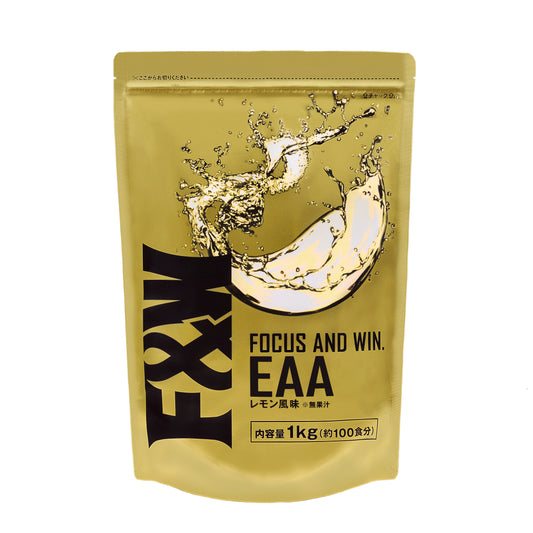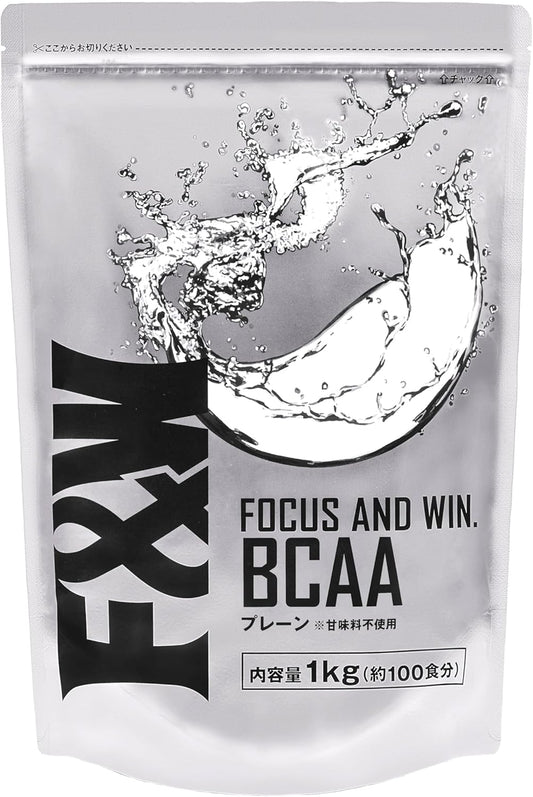アミノ酸100%配合製品なのに裏面のタンパク質表記にアミノ酸以外も含まれる理由とは?
クレアチンやHMBがタンパク質100%として表示されない理由について、詳しく分かりやすく説明します。
まず、タンパク質とはアミノ酸が多数結合した高分子化合物であり、一般的には複数のアミノ酸が結合してできた物質を指します。筋肉を構成する主な成分であり、筋肉の成長や修復に欠かせない栄養素です。一方、クレアチンやHMBはタンパク質そのものではなく、タンパク質を構成するアミノ酸から派生した物質(代謝産物)であり、その働きや性質はタンパク質とは大きく異なります。

具体的にそれぞれの特徴を見ていきましょう。
クレアチンとは何か?
クレアチンは、主に筋肉内に存在している化合物で、無酸素運動(短時間で強度の高い運動)時にエネルギー供給を助ける働きを持っています。筋肉内でエネルギー源となるATP(アデノシン三リン酸)の再合成を促進し、瞬発力や筋力向上に役立つと言われています。つまり、クレアチン自体は筋肉の材料となるタンパク質ではなく、エネルギー生産を助ける補助的な役割を果たす栄養素です。
HMB(β-ヒドロキシ-β-メチル酪酸)は必須アミノ酸であるロイシンの代謝産物であり、筋肉の分解を抑制し、筋肉合成を促進する作用が期待されています。つまり、HMBは筋肉を守り育てる働きを持つ栄養素です。こちらもタンパク質そのものではなく、「ロイシン」というアミノ酸が体内で代謝されて作られる特定の化合物です。
このように、クレアチンやHMBは「タンパク質そのもの」ではなく、「タンパク質を構成する一部のアミノ酸から派生した特定の物質」であるため、「タンパク質100%」と表示されません。食品表示上、「タンパク質」として記載できるのは、多数のアミノ酸がペプチド結合によって連鎖して構造を形成した状態(ポリペプチド)のものに限定されます。つまり、「タンパク質」と呼ぶには一定以上の長さと構造を持ったアミノ酸鎖が必要なのです。

具体的には以下のような違いがあります:
| 成分名 | 種類・性質 | 主な働き(研究報告等) |
|---|---|---|
| タンパク質 | 多数のアミノ酸が鎖状につながった高分子化合物 | 筋肉・骨格・皮膚など身体組織の構築・修復 |
| クレアチン | アミノ酸由来の代謝産物(非タンパク性窒素化合物) | 短時間・高強度運動時のエネルギー供給サポート |
| HMB | ロイシン(必須アミノ酸)の代謝産物 | 筋肉分解抑制・筋合成促進 |
また、市販されているサプリメント製品でも「タンパク質含有量」の表示を見ると、例えばHMBとクレアチンが配合されたサプリメントでも実際に含まれる「たんぱく質」の量は少なく表示されています。これは先述したように、これらが純粋なタンパク質ではないためです。
さらに言えば、食品表示法など法的な観点からも「タンパク質」として表示できるものは明確に定義されています。そのため、「HMB」や「クレアチン」を含んだサプリメントであっても、それらはあくまで「HMBカルシウム」や「クレアチンモノハイドレート」といった個別の成分名で表示されることになります。
-
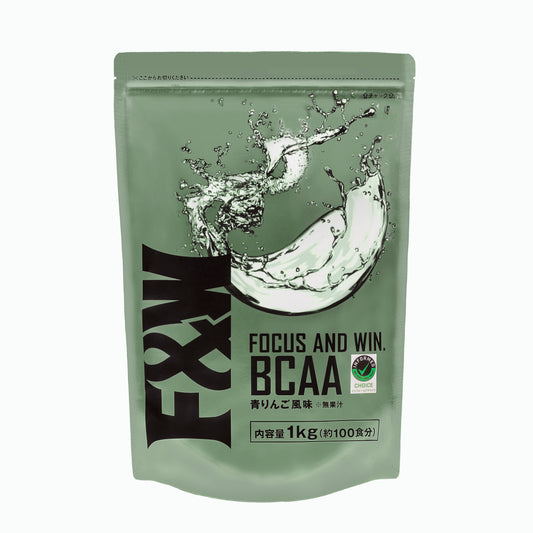 売り切れ
売り切れF&W BCAA 青りんご風味 1Kg
通常価格 ¥3,960通常価格単価 あたり -
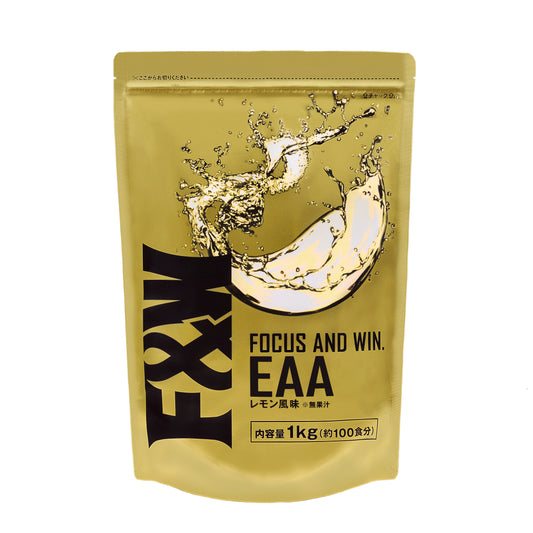 売り切れ
売り切れF&W EAA レモン風味 1Kg
通常価格 ¥5,960通常価格単価 あたり
まとめると、
クレアチンやHMBはタンパク質そのものではなく、「タンパク質を構成する一部のアミノ酸から派生した特定の代謝産物」である。
タンパク質として表示するには一定以上長いアミノ酸鎖構造が必要だが、それらは単独または短い構造しか持たないため、「タンパク質」として分類されない。
法律上もこれらはタンパク質として表示できず、それぞれ固有の名称で表示する必要がある。
以上が、クレアチンやHMBなどが「タンパク質100%」という表記にならない理由です。