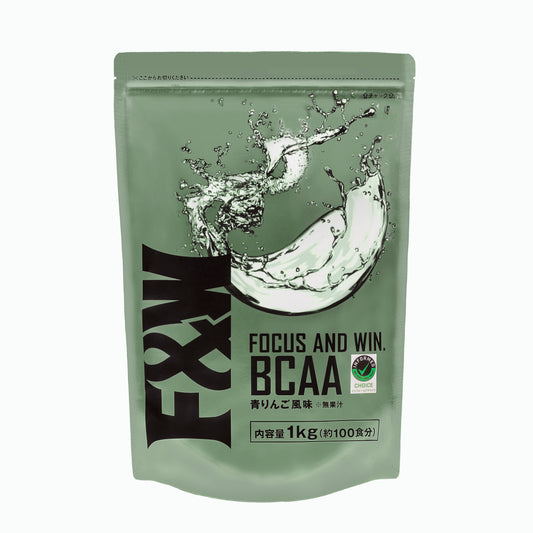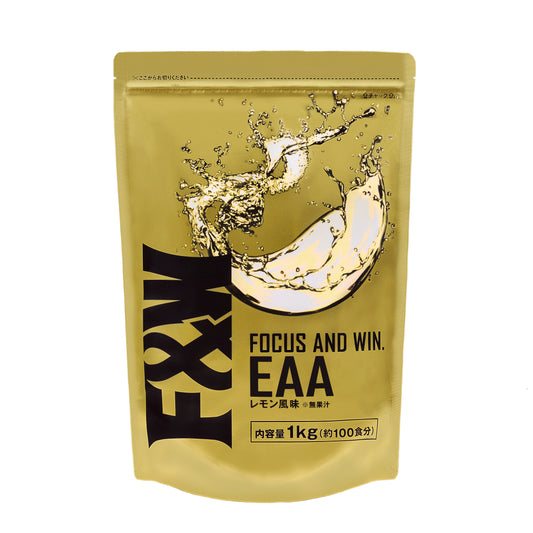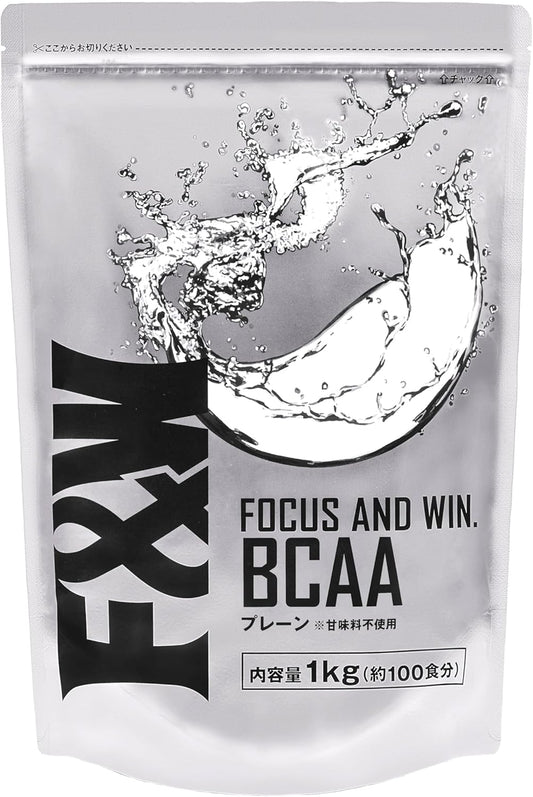シトルリン量がすべてタンパク質としてカウントされない理由とは?アルギニンとの配合剤は?
シトルリンはグルタミンとは異なり、「タンパク質100%」として表記することはできません。
その理由を詳しく説明します。
まず、シトルリンは「遊離アミノ酸」の一種ですが、グルタミンとは決定的に異なる特徴があります。それは、シトルリンが「タンパク質を構成しないアミノ酸」であるという点です。

グルタミンの場合は、タンパク質を構成する20種類のアミノ酸の一つ(タンパク質構成アミノ酸)であり、食品表示法における栄養成分分析(窒素換算法)では、遊離アミノ酸であっても窒素含有量から計算して形式的に「タンパク質」として表示されることがあります。そのため、一部製品ではグルタミンが「タンパク質」として表示される場合があるのです。
しかし、シトルリンの場合はそもそもタンパク質を構成する20種類のアミノ酸には該当せず、体内でタンパク質合成の材料として使われることもありません。シトルリンは主に体内でアルギニンや一酸化窒素(NO)を生成するための前駆物質として働きます。具体的には、オルニチン回路(尿素回路)というアンモニアを解毒する代謝経路の中で重要な役割を担い、一酸化窒素の生成を促進して血管拡張作用や血流改善効果などを発揮することが期待されています。
このように、シトルリンは体内で重要な機能を果たしますが、そもそもタンパク質の構造には含まれないため、生化学的にも食品表示法上でも「タンパク質」として表記することはできません。実際、市販されているシトルリンサプリメントでも、「タンパク質量」と「シトルリン量」は明確に区別して表示されています。
-
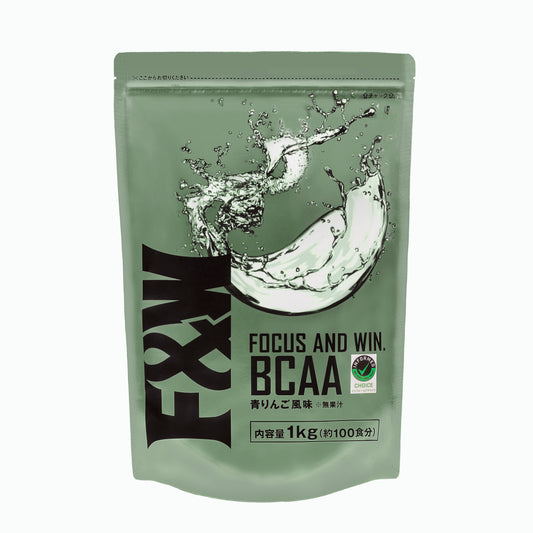 売り切れ
売り切れF&W BCAA 青りんご風味 1Kg
通常価格 ¥3,960通常価格単価 あたり -
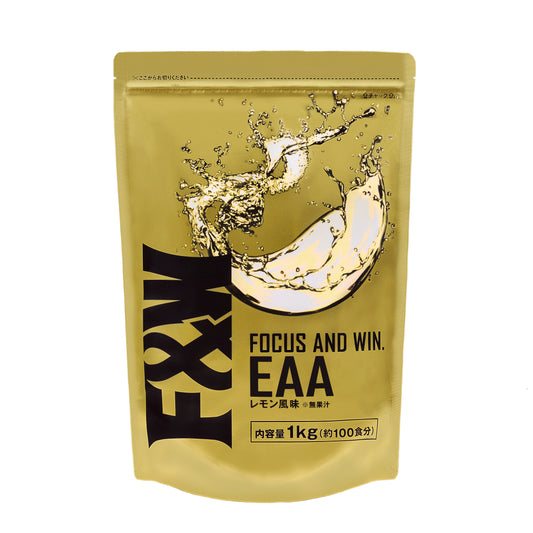 売り切れ
売り切れF&W EAA レモン風味 1Kg
通常価格 ¥5,960通常価格単価 あたり
たとえばアルギニンとシトルリンの粉末を混合した場合、栄養成分表示に記載される「たんぱく質量」は、必ずしも投入したアルギニンとシトルリンの総量すべてが表示されるとは限りません。アルギニンは一般的にタンパク質を構成するアミノ酸であり、栄養成分表示上の「たんぱく質」として計上されます。一方で、シトルリンは遊離アミノ酸であり、生体内でタンパク質合成に直接使われることはなく、主にアルギニンの前駆体として機能します。
しかし、日本の栄養表示基準では、遊離アミノ酸も「たんぱく質」として表示することが認められているため、市販されているアルギニン・シトルリン混合製品では、シトルリンも含めて「たんぱく質」として表示されているケースがあります。
実際、市販されているアルギニンとシトルリンの混合粉末の商品例では、「100gあたりたんぱく質100g」と表示されており、この場合はアルギニンとシトルリン両方の総量がタンパク質として計上されています。

つまり、表示されるタンパク質量はメーカーや製品によって異なりますが、日本国内では一般的にアルギニンとシトルリン両方が「たんぱく質」として表示される傾向があります。
ただし、生理学的な観点から見ると、シトルリンは直接タンパク質合成には利用されないため、生体内での実効的なたんぱく質合成量とは必ずしも一致しないことになります。
まとめると次のようになります:
シトルリンは遊離アミノ酸だが、「タンパク質を構成しない」特殊なアミノ酸である。
グルタミンは実際にタンパク質を構成するアミノ酸であり、分析方法(窒素換算法)の関係で形式的に「たんぱく質」と表記される場合がある。一方、シトルリンはそもそもタンパク質中には存在しないため、そのような扱いにならない。
そのため、シトルリンはグルタミンと異なり、「たんぱく質100%」という表記はできず、「シトルリン100%」と表記される場合でも、それはあくまで純度や配合割合を示す意味合いとなります。
結論として、シトルリンはグルタミンと異なり、「タンパク質100%」という表記を行うことはできません。