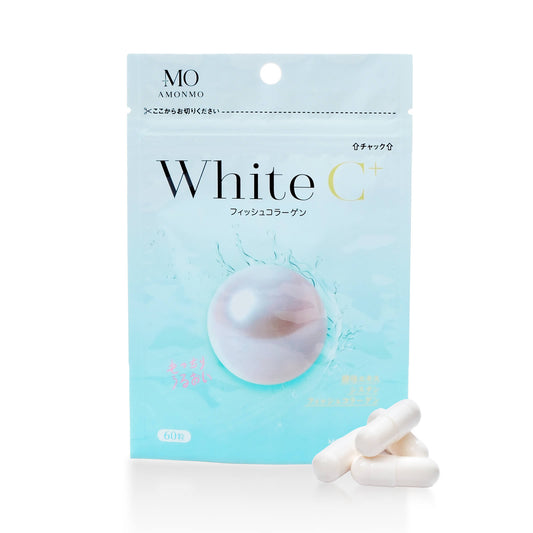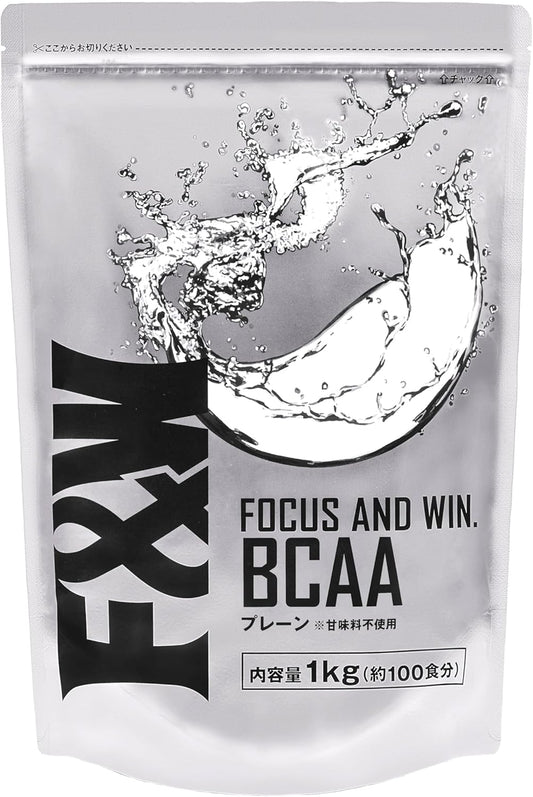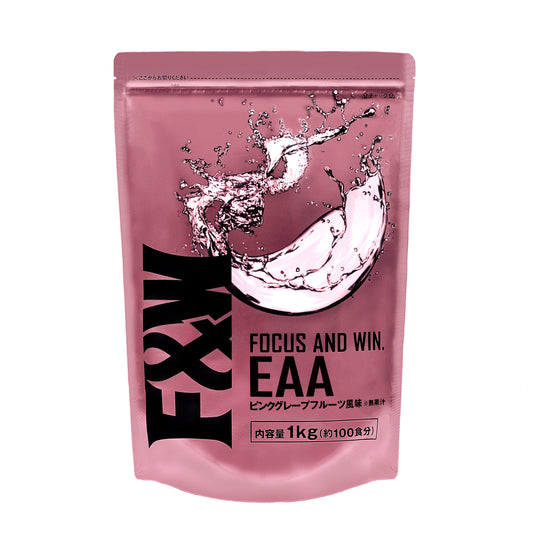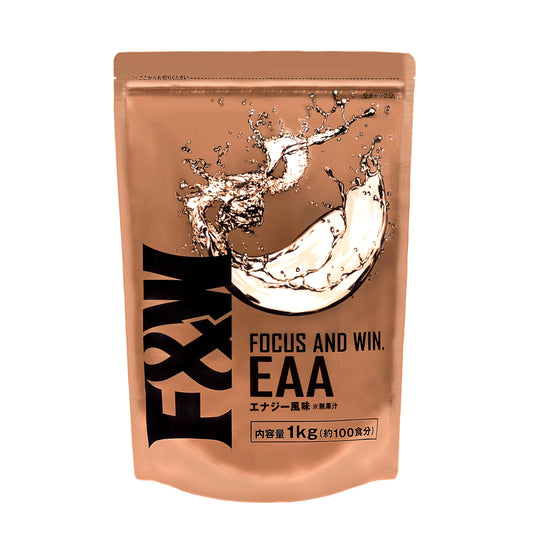お酒を深夜まで飲んでから翌日健康診断に行くとどういう弊害があるの?
「健康診断前日だけど、まあ少しぐらいなら大丈夫だろう」
そんな軽い気持ちで深夜まで飲んでしまい、翌日の健康診断で思わぬ異常値が出てしまった――このような経験をお持ちの方は少なくありません。健康診断は、現在の健康状態を客観的に把握するための重要な機会ですが、前日の飲酒によって検査結果が正確に反映されず、再検査や誤診のリスクにつながることもあるのです。
この記事では、深夜まで飲酒してから翌日健康診断を受けることで生じる具体的な弊害について、検査項目ごとに詳しく解説します。

なぜ前日の飲酒が問題になるのか
アルコールを摂取すると、血液中のアルコール濃度が上昇し、数時間から長ければ半日ほどの時間をかけて元に戻ります。特に深夜まで飲酒した場合、翌朝の健康診断までにアルコールが完全に代謝されず、体内に残っている可能性が高くなります。
厚生労働省の「標準的な健診・保健指導プログラム」でも、アルコールは健診の前日から控えることとされています。これは、アルコールが肝臓をはじめとする複数の臓器に負担をかけ、検査結果に多岐にわたる影響を及ぼすためです。
肝機能検査への深刻な影響
深夜までの飲酒が最も顕著に影響するのが肝機能検査です。
γ-GTP(ガンマGTP)の異常上昇
γ-GTPはアルコールに最も敏感に反応する検査項目で、少量の飲酒でも異常値になることがあります。特に深夜まで飲酒した場合、翌朝までにγ-GTPが基準値を大きく超えることが多く、肝疾患の疑いが出てしまいます。通常、γ-GTPの基準値は50 IU/L以下とされていますが、前日の飲酒だけで数値が倍増することも珍しくありません。
AST(GOT)・ALT(GPT)の上昇
肝臓の細胞がダメージを受けた際に上昇するAST(GOT)やALT(GPT)も、飲酒によって一時的に上昇します。これらの数値が高いと、肝炎や脂肪肝の兆候と誤認されることがあり、精密検査や再検査の対象となる可能性が高まります。肝臓はアルコール分解の中心的な役割を担っているため、深夜まで飲酒すると肝臓への負担が大きくなり、検査時にはまだ回復していない状態で測定されることになります。
血液検査への多面的な影響
中性脂肪の急上昇
アルコールには糖質が多く含まれており、飲酒によって中性脂肪が一時的に急上昇します。特に深夜まで飲酒した場合、翌朝の検査時にまだ中性脂肪が高い状態が続いていることがあります。基準値は150mg/dL未満とされていますが、前日の飲酒だけで200mg/dLを超えることもあり、脂質異常症の疑いが出てしまいます。

さらに、脂質の高いおつまみを食べながら飲酒した場合、中性脂肪の数値はさらに高くなりやすく、検査結果に二重の悪影響を与えます。
血糖値の変動
アルコールは血糖値の変動を引き起こす可能性があります。飲酒直後は血糖値が上昇しますが、その後インスリンの作用により急激に低下することもあり、検査のタイミングによって血糖値が通常とは異なる値を示すことがあります。特に糖尿病の診断においては、正確な血糖値の測定が不可欠であるため、前日の飲酒は避けるべきとされています。
尿酸値の上昇
アルコールは体内で代謝される過程で尿酸の生成を促進し、さらに尿酸の排泄を阻害する作用があります。そのため、深夜まで飲酒すると尿酸値が上昇し、痛風や高尿酸血症のリスクがあると判定されることがあります。基準値は7.0mg/dL以下ですが、飲酒により一時的に8.0mg/dL以上になることも珍しくありません。
脱水による検査値の変化
アルコールには強い利尿作用があり、飲酒すると体内の水分が失われやすくなります。深夜まで飲酒した場合、翌朝には脱水状態になっていることが多く、これが検査結果に影響を及ぼします。
血液濃度の変化
脱水状態では血液が濃縮され、尿素窒素やヘマトクリット(血液中の赤血球の割合)が高くなりやすくなります。これらの数値が高いと、腎機能の低下や多血症の疑いが出ることがあり、実際の健康状態とは異なる診断につながる可能性があります。
尿検査への影響
脱水状態では尿が濃縮されるため、尿中の蛋白や糖の濃度が実際よりも高く検出されることがあります。また、アルコールの代謝産物が尿中に排泄されることで、尿検査の結果に影響が出ることもあります。
循環器系検査への影響
血圧の上昇
アルコールを摂取すると一時的に血管が拡張しますが、その後血管が収縮して血圧が上昇することがあります。深夜まで飲酒した場合、翌朝の健康診断時にまだ血圧が高い状態が続いていることがあり、高血圧の疑いが出ることがあります。さらに、飲酒による睡眠不足や二日酔いの体調不良も血圧を上昇させる要因となります。
心拍数の変動
アルコールは心拍数にも影響を与え、飲酒後は心拍数が上昇することがあります。健康診断の心電図検査では、心拍数の異常やリズムの乱れが記録されることがあり、不整脈などの心疾患が疑われる可能性があります。
消化器系への影響
アルコールは胃腸にも影響を与え、消化器系の検査結果を変える可能性があります。特に大量の飲酒は胃粘膜を刺激し、炎症を引き起こすことがあります。極端な場合、飲み過ぎによって食道が傷つき出血する「マロリーワイス症候群」などが発生することもあり、便潜血検査や胃のバリウム検査に影響が出ることがあります。
-
AMONMO WhiteC+ 60粒(グルタチオン含有酵母抽出物配合)
通常価格 ¥2,650通常価格単価 あたり -
F&W アルギニン シトルリン クエン酸 ゆず風味 250g
通常価格 ¥2,750通常価格単価 あたり -
F&W グルタミン パウダー ノンフレーバー 500g
通常価格 ¥1,980通常価格単価 あたり
再検査・精密検査のリスク
前日の飲酒が原因で異常値が出た場合、再検査や精密検査の対象となることがあります。これは時間的・経済的な負担となるだけでなく、精神的なストレスにもつながります。
再検査になりやすい項目
以下の検査項目は、前日の飲酒によって基準値を外れやすく、再検査の対象になる可能性が高いとされています。
γ-GTP: 肝臓のアルコール代謝で上昇し、再検査になる可能性が非常に高い項目です。
中性脂肪: 飲酒による脂質代謝の乱れで上昇し、再検査の可能性が高い項目です。
尿酸値: アルコールによる代謝促進で上昇し、中程度の確率で再検査の対象となります。
血糖値: 飲酒後のインスリン反応で変動し、中程度の確率で再検査の対象となります。
誤診のリスク
より深刻な問題は、一時的な数値の変化が実際の病気と誤認されるリスクです。医師に飲酒の申告がないまま異常値が出ると、医師は病気の疑いを強く持たざるを得ず、不要な治療や通院が始まることもあります。正確な診断を得るためにも、飲酒の影響を排除した状態で検査を受けることが重要です。
適切な禁酒期間はどれくらい?
では、健康診断の何時間前から飲酒を控えるべきなのでしょうか。

24時間前からの禁酒が理想
医療機関や検査項目によって多少の違いはありますが、一般的には検査の24時間前から禁酒が推奨されています。たとえば、午前9時に健康診断がある場合は、前日の朝9時以降は飲酒を控えるのが理想です。
肝臓がアルコールを分解するのに要する時間は、日本酒1合換算(純アルコール約20g)で約3時間かかります。しかし、飲酒量が多い場合や深夜まで飲酒した場合は、代謝に時間がかかるため、24時間前からの禁酒でも不十分なことがあります。
検査項目別の推奨禁酒時間
検査項目によって、飲酒の影響が現れやすさや持続時間が異なります。
肝機能検査(AST/ALT/γ-GTP): アルコールの影響が最も顕著に現れる項目で、24時間前からの禁酒が推奨されます。
脂質検査(中性脂肪): 飲酒で中性脂肪が急上昇するため、12〜24時間前からの禁酒が推奨されます。
血糖値・尿酸値: 飲酒後の代謝変化で数値が乱れるため、12時間以上前からの禁酒が推奨されます。
深夜まで飲んでしまった場合の対処法
もし前日の深夜まで飲酒してしまった場合は、翌朝の体調を確認しましょう。頭痛や倦怠感、顔色の悪さ、目の充血などがある場合は、アルコールがまだ体内に残っている可能性が高いため、正直に医療機関に申告することをおすすめします。場合によっては、健康診断の日程を変更してもらえることもあります。
飲酒以外にも気をつけるべきこと
健康診断前日は、飲酒だけでなく他の生活習慣にも注意が必要です。
食事の時間と内容
健康診断の10時間前からは絶食が基本です。特に脂質の高い食事は中性脂肪の数値に影響を与えるため、前日の夕食は軽めにすることが推奨されます。揚げ物や脂身の多い肉、バターやチーズなどの乳製品は控えめにしましょう。
清涼飲料水や甘い飲み物
糖類がたっぷり入った清涼飲料水は、血糖値を上昇させるため、当日朝は摂取しないよう気をつけてください。前日から過度な摂取は控えるべきです。
カフェインを含む飲み物
コーヒー、紅茶、緑茶などカフェインを多く含む飲み物も、前日に過剰に摂取したり当日朝に飲むことは控えましょう。カフェインは血圧や心拍数に影響を与える可能性があります。
喫煙
喫煙者は、飲酒と同様に前日からやめておくのが好ましいとされています。タバコに含まれているニコチンは血管を収縮させてしまうため、血圧検査において高い数値を出す可能性があります。
激しい運動
前日の激しい運動は、筋肉からの酵素が血液中に流れ出し、肝機能検査の数値に影響を与えることがあります。軽い散歩程度なら問題ありませんが、筋力トレーニングやマラソンなどの激しい運動は控えましょう。
まとめ:正確な健康診断のために
深夜まで飲酒してから翌日健康診断を受けると、肝機能検査、血液検査、尿検査、循環器系検査など、ほぼすべての検査項目に影響が出る可能性があります。これらの影響は、再検査や精密検査の対象となるだけでなく、誤った診断につながるリスクもあります。
健康診断は、現在の健康状態を正確に把握し、病気の早期発見・早期治療につなげるための重要な機会です。前日の飲酒によって検査結果が歪められてしまうと、せっかくの機会が無駄になってしまいます。
健康診断の24時間前からは禁酒し、食事や睡眠などの生活習慣にも気を配ることで、正確な診断結果を得ることができます。「少しぐらいなら大丈夫」という軽い気持ちではなく、自分の健康を正しく知るための準備として、前日の過ごし方を意識してみてはいかがでしょうか。