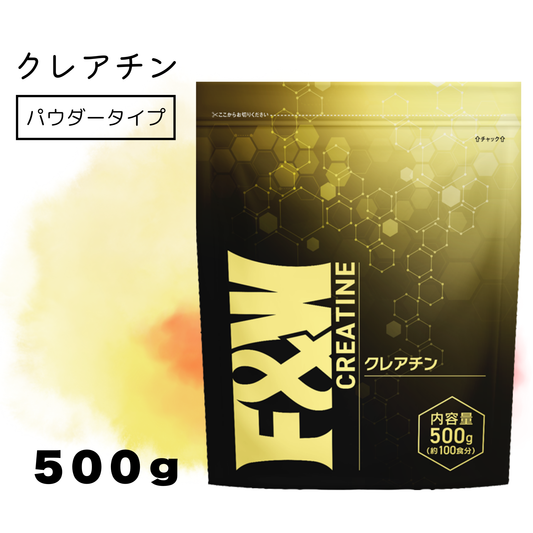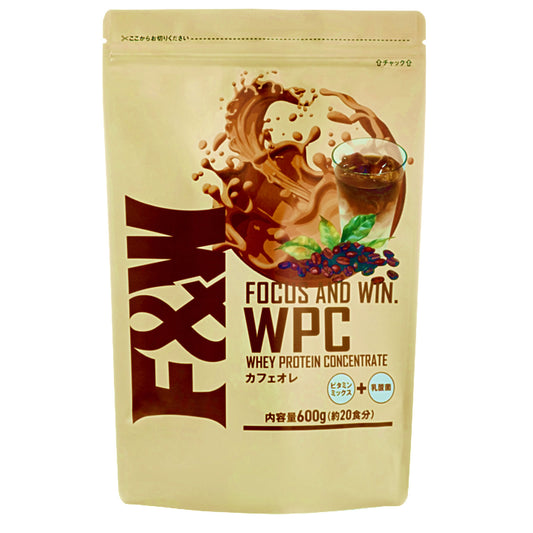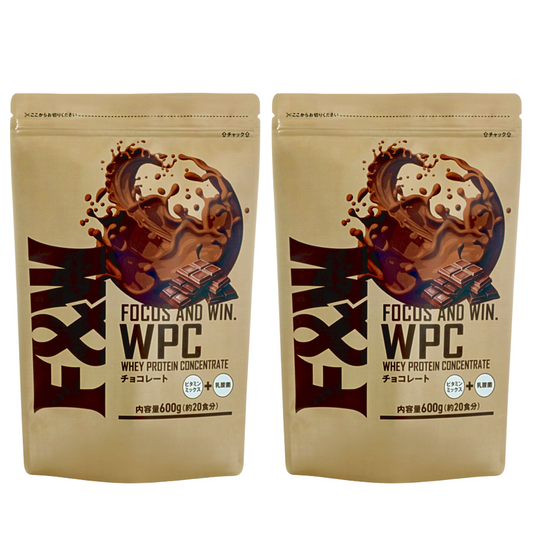オーバートレーニング症候群とは具体的にどういう症状なの?
オーバートレーニング症候群とは
オーバートレーニング症候群(Overtraining Syndrome, OTS)は、スポーツや運動において過度なトレーニング負荷を長期間にわたり繰り返し、身体的・精神的な回復が不十分なまま疲労が蓄積し続けることで発症する慢性疲労状態を指します。単なる一時的な疲労(オーバーワーク)とは異なり、休息を取っても容易に回復せず、競技パフォーマンスの低下や多彩な心身の不調が長期間持続します。

発症のメカニズム
トレーニングの基本原則である「負荷と回復のバランス」が崩れ、回復が追いつかないまま過剰な負荷を継続することで発症します。
筋肉や神経系、ホルモン、自律神経、免疫系など多方面に影響が及びます。
特に真面目で責任感が強い人、休むことに罪悪感を持つ人が陥りやすい傾向があります。
症状の経過と特徴
オーバートレーニング症候群の症状は段階的に進行し、初期は気付きにくいものの、次第に全身にさまざまな不調が現れます。
1. 初期症状
競技成績やパフォーマンスの低下(記録の伸び悩み)
トレーニング後の疲労感が抜けにくい
軽い運動でも疲れやすくなる
2. 進行期の症状
身体が思うように動かない、動作が重い
全身倦怠感、疲労感の増強
睡眠障害(入眠困難、中途覚醒など)
食欲低下、体重減少
集中力低下、注意力散漫
安静時心拍数の増加、血圧上昇、運動後の血圧回復の遅延
免疫機能低下(風邪をひきやすい、治りにくい)
自律神経の不調(立ちくらみ、動悸、息切れ、めまい)
3. 重症化した場合
抑うつ気分、意欲低下、気持ちの落ち込み
不安感、精神的な疲労感
競技や日常生活への興味喪失
長期化すると数か月から年単位で回復に時間がかかることもある

診断と除外診断
オーバートレーニング症候群は、他の疾患(貧血、感染症、内分泌異常など)を十分に除外した上で診断されます。
心理テスト(POMSなど)や心拍数・血圧の変化、血液検査などが参考にされます。
原因・誘因
過度なトレーニング負荷(頻度・強度・量が多すぎる)
休養・睡眠不足
栄養不足(特にタンパク質、炭水化物、ビタミンなど)
精神的ストレスやプレッシャー
外的環境要因(気候、生活リズムの乱れなど)
予防と対応
トレーニングと休息・栄養のバランスを重視する
定期的に自分の体調やパフォーマンスをチェックする
疲労や不調を感じたら、早めに運動量を調整し、必要なら休養を取る
症状が出た場合は医療機関を受診し、他疾患の除外と適切な指導を受ける
-
F&W WPC ベリー風味600g
通常価格 ¥3,980通常価格単価 あたり -
F&W クレアチンパウダー 500g
通常価格 ¥2,480通常価格単価 あたり -
F&W グルタミン パウダー ノンフレーバー 500g
通常価格 ¥1,980通常価格単価 あたり
回復の経過
オーバートレーニング症候群の回復には、十分な休息と栄養、ストレス管理が不可欠です。
軽症なら数週間、重症例では数か月から年単位で回復に時間がかかることがあります。
早期発見・早期対応が予後を大きく左右します。
まとめ
オーバートレーニング症候群は、過度なトレーニングと不十分な回復が重なり合うことで、心身に慢性的な疲労と多彩な不調をもたらす状態です。初期はパフォーマンス低下や疲労感から始まり、進行すると全身倦怠感や精神症状まで発展します。回復には十分な休息と適切な対応が不可欠であり、予防のためには「自分の身体の声を聴く」ことが最も重要です。