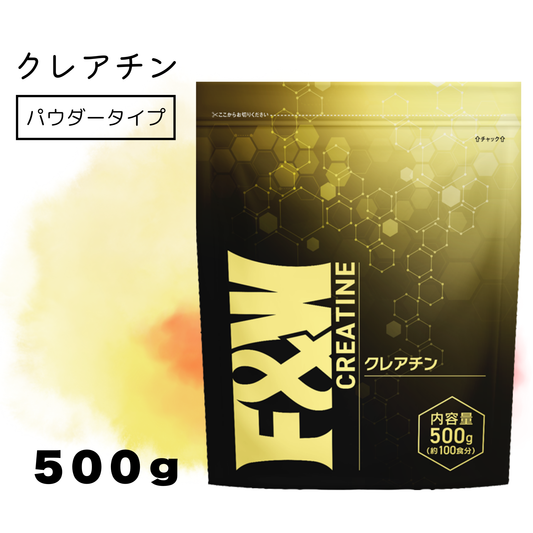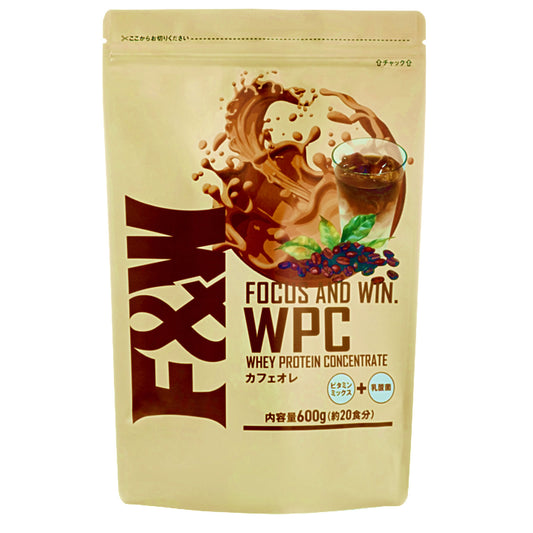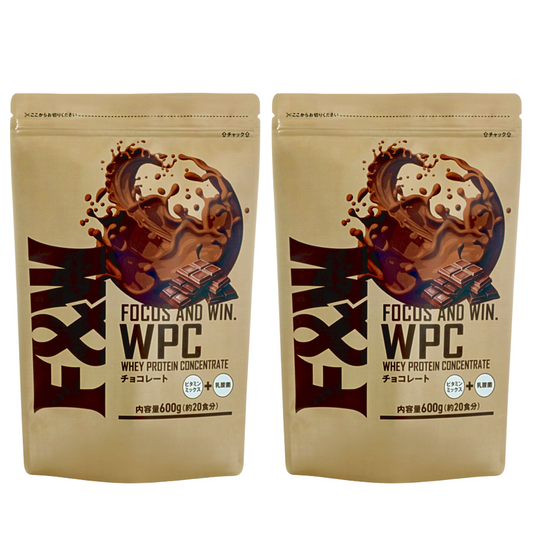最近、コンビニの商品でも「タンパク質〇〇g!」という表示を見かけますが何故?
近年、コンビニエンスストアで「たんぱく質○g」といった表示が目立つ食品が急増している背景には、明確な需要の高まりと、それに応じた市場拡大が存在します。
需要拡大の背景
1. 健康志向とライフスタイルの変化
日本国内でも健康志向が一層高まり、特に筋トレやダイエット、体型維持を意識する層が増えています。こうした層は、筋肉の維持や代謝促進に不可欠な栄養素としてタンパク質の摂取量を意識する傾向が強くなりました。従来はアスリートや一部の健康マニア層が中心でしたが、今や一般層にも「日常的にタンパク質を意識する」習慣が広がっています。

2. 市場規模の急拡大
富士経済の調査によれば、日本のプロテイン飲料や高タンパク食品を含むタンパク補給食品市場は、2023年に約2,580億円(見込み)と、この10年で約4倍に拡大しています。この成長は、コンビニ各社が高タンパク食品を積極的に品揃えに加えたことと密接に関連しています。
3. 商品開発とマーケティング戦略
コンビニ各社や食品メーカーは、健康志向の高まりを受けて「サラダチキン」「プロテインバー」「高タンパク飲料」など多様な商品を開発し、手軽にタンパク質を補給できる環境を整えました。特に森永製菓の「inゼリー プロテイン」や、豆腐メーカーによる「豆腐バー」などが大ヒットし、商品バリエーションも飛躍的に増加しています。
4. グローバルトレンドの影響
海外のプロテインブームや健康食品市場の動向も日本市場に大きな影響を与えています。ローソンやファミリーマートは、海外ブランドやトレンドを積極的に導入し、日本の消費者にも「プロテイン食品=日常的な選択肢」という認識が定着しつつあります。

消費者のニーズと価格感覚
実際にコンビニ利用者を対象とした調査でも、たんぱく質強化食品に対して「多少価格が上がっても購入したい」という意識が見られ、30円前後の価格上昇を「適正」と感じる消費者が多いことが分かっています。これは、健康価値や機能性に対して追加コストを支払う消費者心理が広がっていることを示しています。
今後の展望と社会的背景
世界的には「タンパク質危機(プロテインクライシス)」という、人口増加に対してタンパク質供給が追いつかなくなる社会課題も議論されています。こうした中、環境負荷の低い植物性タンパクや代替肉、昆虫食などの新たなタンパク源の開発・普及も進んでおり、今後もタンパク質需要はさらに高まると予想されます。
-
F&W WPC ベリー風味600g
通常価格 ¥3,980通常価格単価 あたり -
F&W クレアチンパウダー 500g
通常価格 ¥2,480通常価格単価 あたり -
F&W グルタミン パウダー ノンフレーバー 500g
通常価格 ¥1,980通常価格単価 あたり
まとめ
コンビニでタンパク質量を強調した食品が増えているのは、単なる流行ではなく、健康志向の高まりと市場の拡大、消費者ニーズの多様化、そしてグローバルトレンドの影響を背景とした「需要の伸び」の明確な現れです。今後もこの傾向は続き、タンパク質表示は食品選びの新たなスタンダードとなっていくでしょう。