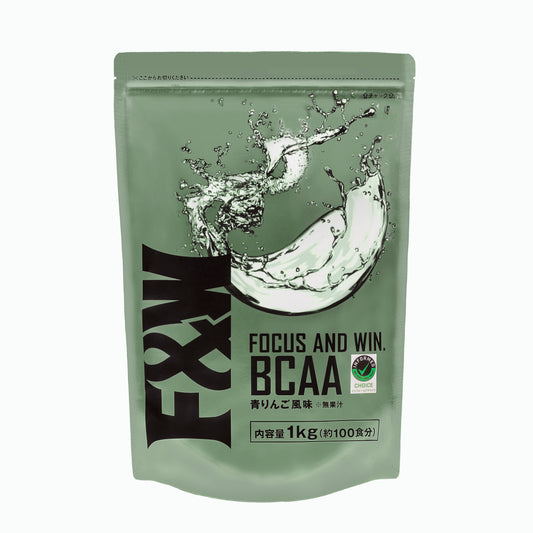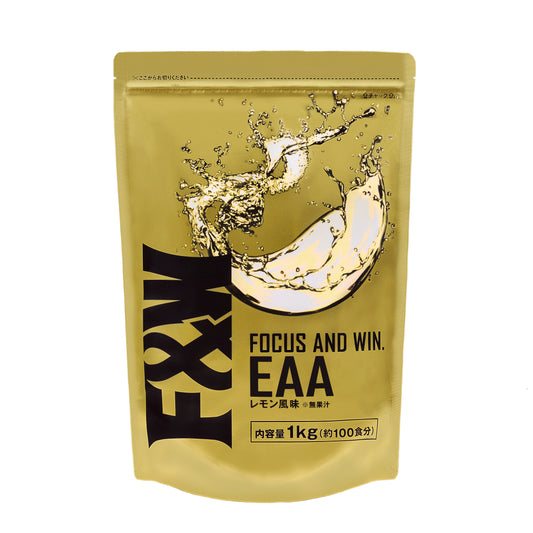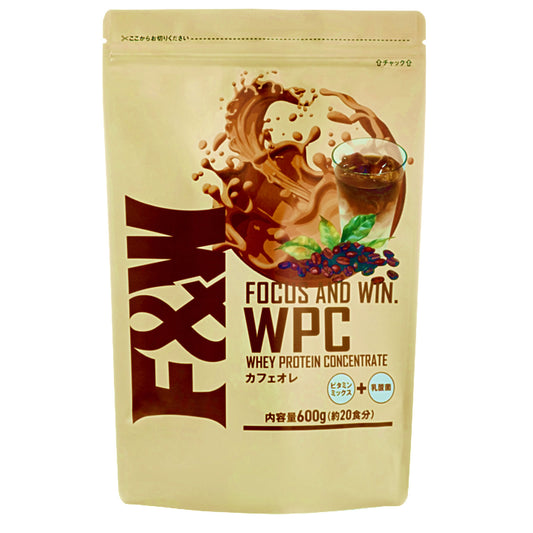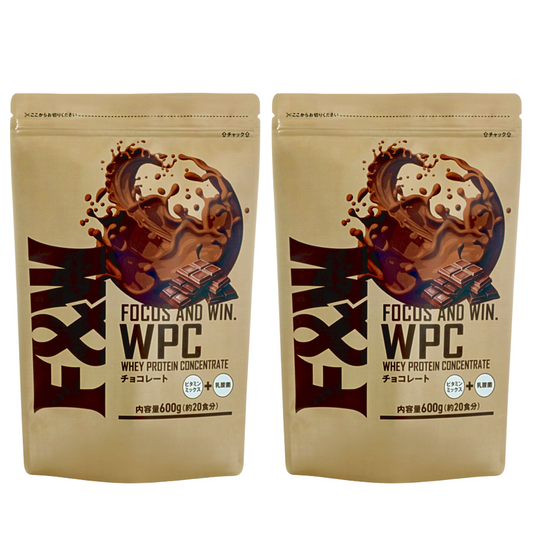不要不急時でもトレーニングは欠かしたくない方へのメソッド
不要不急の外出を控えなければならない状況でも、筋力や健康状態を維持・向上させるためにトレーニングを行うことは非常に有意義です。以下では、国内外の専門機関が推奨・紹介している情報を踏まえながら、主に在宅で行えるトレーニング内容や工夫、注意点などをなるべく詳しくまとめました。
1.不要不急時でも取り組む意義と基本的な考え方
1-1.活動量低下による弊害とトレーニングの重要性
外出自粛・リモートワーク・避難生活などで長期的に活動量が低下すると、筋力・持久力の低下、生活習慣病リスクの上昇、うつ傾向など心身に悪影響が及ぶとされています。
特に高齢者は「生活不活発病」やサルコペニア(加齢に伴う筋肉量の低下)が進みやすく、転倒・要介護リスクも増大しかねません。
自宅で実施できる運動・スポーツを習慣化することで、体力を維持し、感染症や災害時の備え(防災筋力)にもつながります。

1-2.トレーニング頻度と継続のポイント
運動実施の目安として「週2~3回以上の頻度」「1回あたり15~30分以上の継続」が推奨されることが多いですが、まずは細切れの運動を積み重ねる形でも十分効果が期待できます。
継続のコツとして「ながら運動」「細切れ運動」「三日坊主OKで再開を繰り返す」ことが推奨されています。大きな負担ではなく、日常動作に組み込みやすい運動を、無理のない範囲で継続することが重要です。
運動強度や時間よりも「まずは頻度を下げずに実施する方が、筋力や体力低下が少ない」という研究報告もあります8。体調やストレスを考慮しつつ、できるだけ強度を大きく下げすぎない形で工夫しましょう。
2.在宅でできる運動の具体例
2-1.自重トレーニング(筋力維持・向上)
スクワット
太ももやお尻、体幹を同時に鍛えられる定番種目。
4秒かけて腰を落とし、4秒かけて戻すなど、ゆっくり行いましょう。
膝や腰の負担を減らしたい場合、椅子につかまりながら行う、または浅めの動作に調整します。

もも上げ(ヒップフレクサー・大腰筋系エクササイズ)
椅子やテーブルにつかまりながら片脚をゆっくり引き上げ、体幹と股関節周りを強化。
座位姿勢でのもも上げ(椅子に座ったまま片膝を引き上げる)でも可。
プランク
うつ伏せで肘を床についたまま体を一直線に保つ。腹筋群、背筋、肩周りも鍛えられます。
20~30秒を1セットとして、慣れてきたら時間やセット数を増やす。
椅子スクワット・壁スクワット
足腰が弱い方は椅子に座る→立ち上がる動作を繰り返したり、壁に背中をつけて腰をゆっくり下ろす方法がおすすめ。
かかと上げ(カーフレイズ)
ふくらはぎ筋を鍛え、血行促進や足首の安定を図る。
立ちながら、かかとを上げ下げをゆっくり10~15回。家事の合間にも取り入れやすい。
2-2.ながら運動・日常動作の活用
家事をしながら:例えばキッチンで洗い物をしながら重心移動、かかと上げ、片脚立ち。
テレビやラジオを聞きながら:その場足踏み、椅子に座っての腹筋運動など。
電話や歯磨き中につま先立ちやスクワット、簡単なストレッチを挟む。
エレベーターやエスカレーターを使わず階段をできる範囲で活用。通勤や買い物で歩行を増やす。
2-3.有酸素運動
屋外でウォーキングやジョギングを行う際は、「人との距離をしっかり保つ」「混雑を避ける」「マスク等で飛沫を防ぐ」などの感染対策が必要です。
天候や感染状況を考慮し、難しい場合はステップ運動(階段昇降や踏み台昇降)を室内で行う方法もあります。
-
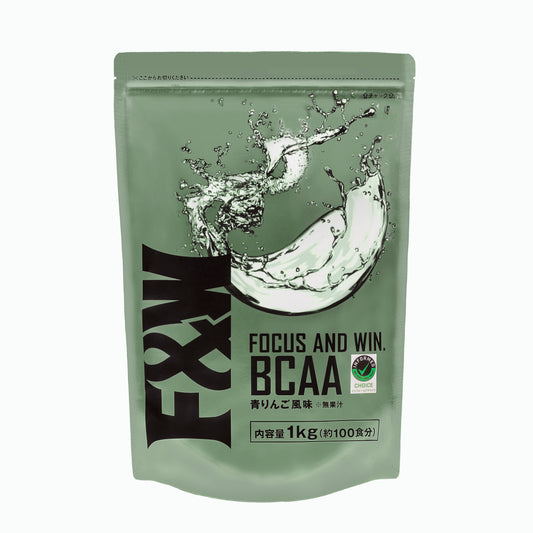 売り切れ
売り切れF&W BCAA 青りんご風味 1Kg
通常価格 ¥3,960通常価格単価 あたり -
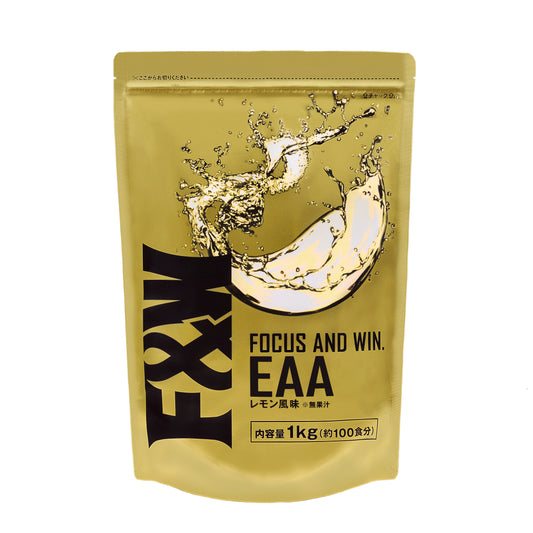 売り切れ
売り切れF&W EAA レモン風味 1Kg
通常価格 ¥5,960通常価格単価 あたり
3.トレーニングを継続するための工夫
3-1.「細切れ&ながら運動」の意義
1回10~20分のまとまった時間がとりにくい場合、小刻み(5分や10分刻み)でもこまめに行うのが効果的です。
細切れの運動でも合計時間が1日30分を上回れば高血圧や体重減少などの効果が認められています。
3-2.記録や仲間作り
室内トレーニングのメニューや回数、時間などを手帳やアプリに記録すると達成感が高まりやすく、三日坊主防止につながります。
家族やオンラインで仲間をつくり、励まし合う・報告し合うのも継続に有効です。
3-3.強度管理と健康チェック
始めはきつい運動強度を避け、「楽~ややきつい」程度(心拍数や呼吸が少し上がる程度)から始めましょう。
体調不良や痛みが強い日は無理をせず中断し、様子を見て再開します。
疾患(高血圧、心疾患、整形外科的疾患など)がある方は、事前に医療専門家や理学療法士等に相談することが望ましいです。
4.安全に行うための注意点
準備運動・整理運動(ストレッチ)の実施
運動前後には肩回し、胸・背中・太もも周りなどの軽いストレッチを行い、怪我や筋肉痛を予防します。
水分補給と室温調節
冬は暖房で乾燥しやすく、夏は熱中症に注意が必要。室内でも運動中はこまめに水分補給しましょう。
正しいフォームと無理のない負荷
自重トレーニングでもフォームが崩れると筋肉や関節への負担が高まります。腰や膝を傷めない姿勢を確認しながら行いましょう。
5.まとめ
不要不急の外出や長期の自粛要請下であっても、生活の中で可能な範囲のトレーニングを取り入れることで、筋力・体力低下による健康リスクを予防できます。
「ながら運動」や「細切れ運動」を活用し、週2~3回以上を目安に少しずつ負荷を増やしながら継続することが大切です。
過度な負荷はケガや体調不良を招きますので、無理をせずこまめな体調チェック、ストレッチ、十分な休息や栄養の確保にも留意してください。
日常の小さな積み重ねが、筋力・健康維持とストレス解消につながります。ぜひ楽しみながら続けられる方法を見つけてみてください。